はじめに
医療法人を承継するうえで、避けては通れないのが「出資持分」の問題。
「出資持分あり」と「出資持分なし」のどちらを選択するか調べてみたので簡単に解説する。
本記事では、それぞれの特徴、法的・財務的な違い、そして具体的なメリット・デメリットを整理した。
目次
出資持分あり医療法人とは?
概要
出資持分ありの医療法人とは、医療法人社団のうち社員(出資者)が出資に応じた財産的権利=持分を有している法人。かつてはすべての医療法人がこの形式だった。
現在では原則として新設はできない(経過措置型)が、旧法下で設立された法人については引き続き存在している。
特徴
- 法人解散時に残余財産の分配を受ける権利(出資額に応じた払い戻し権)を持つ
- 出資者(理事長や一族)が法人の実質的オーナーになる
- 相続時に持分が相続財産として課税対象になる
出資持分なし医療法人とは?
概要
出資持分なしの医療法人とは、社員が出資をしても持分(財産的権利)を持たない医療法人のこと。
2006年の医療法改正以降、新設可能な医療法人は原則すべて持分なし。旧来の持分あり医療法人も、自主的に移行することが可能(ただし課税問題がある)。
特徴
- 解散時に残余財産は国や自治体等に帰属(社員に返還されない)
- 出資に対する経済的リターンはない
- 持分がないため、相続税の課税対象とならない
メリット・デメリットの比較
| 比較項目 | 出資持分あり医療法人 | 出資持分なし医療法人 |
|---|---|---|
| 解散時の財産分配 | 出資比率に応じて社員へ分配 | 分配なし(公共機関へ帰属) |
| 相続税課税対象 | 出資持分が相続財産として課税対象 | 相続税課税なし(持分が存在しないため) |
| 設立の可否 | 原則として不可(既存法人のみ) | 現行制度で新設可能 |
| 資産の私有性 | 高い(オーナー的運営が可能) | 低い(非営利・公共性が強調される) |
| 承継の自由度 | 高い(親族内承継しやすい) | 低い(理事選任に理事会や評議員会の関与が必要) |
| 法人売却(M&A) | 実質的に売却可能(出資持分の譲渡による) | 売却不可(出資持分がないため資産移転できない) |
| 移行時の税負担 | – | 出資金額が高額な場合、みなし贈与税が発生することがある |
なぜ今「持分なし」への移行が推奨されるのか?
2006年以降、国は非営利性の担保と透明性の確保を理由に「持分なし医療法人」を推進。近年では金融機関・税理士・M&A業者などからも、「将来の相続対策」として持分なしへの移行を勧められるケースが増えている。
ただし、移行時には出資額に応じたみなし贈与税が課税される可能性があるため、注意が必要。
実際の運用上での使い分けは?
出資持分あり医療法人が向いているケース
- 一族経営を維持しながら自由度の高い経営を行いたい場合
- 将来的に法人の売却も視野に入れている場合
- 相続税対策が済んでおり、移行による贈与税負担を避けたい場合
出資持分なし医療法人が向いているケース
- 相続時のリスクを避けたい(贈与税・相続税をゼロにしたい)
- 公共性や非営利性を前面に出した経営スタイルを取りたい
- 法人の長期安定運営を優先したい(属人的な支配を回避したい)
まとめ
| ポイント | 出資持分あり | 出資持分なし |
|---|---|---|
| 所有構造 | オーナー型 | 公益型 |
| 節税効果 | 相続税対策が難しい | 相続税ゼロ |
| 柔軟性 | 高い | 低い |
| 経営承継 | スムーズ | 煩雑(理事会承認) |
ただし、M&Aや相続の際にはさまざまなスキームも存在し、明確なメリットデメリットはない。
 あざらし
あざらし出資持分ありの医療法人は解散した時に非課税で手元に資金が入るため、将来自分の代で医療法人を閉じる予定がある方は出資持分ありを選択するとよい。ただし、承継の際には譲渡価格がクリニック内の資産に応じて上がり、M&A仲介手数料が上がるという詐欺的なことが起こるので注意が必要。
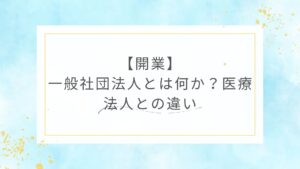
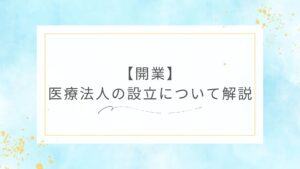
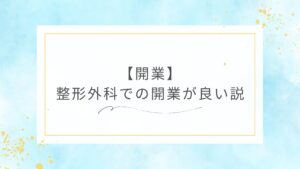
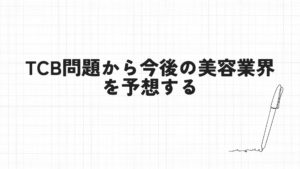
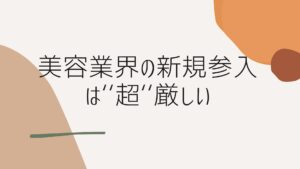
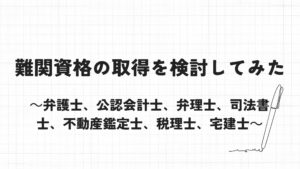


コメント