- 狩猟採集→農耕→産業革命→資本主義という歴史の中で、「労働」は人類にとって本質的・普遍的な営みではなかった可能性
- AIとロボティクスにより、仕事は「奪われる」か「解放される」かの二極化へ
- 予測されるのは、AIを使いこなす少数が富と権力を独占するスーパー格差社会の進行と、その裏面としてベーシックインカム的な再分配が同時進行する未来
- 会社が担ってきた「宗教的役割」(共同体・出会い・儀式・自己実現)が分解し、労働は賃金獲得と自己表現に分離
- 10〜20年は「労働哲学」を各自が持つ時代。働くか否か、働くなら何を意味づけるかを自分で選ぶ
1. 労働は人間にとって“当たり前”ではないという視点
人類史をさかのぼると、狩猟採集期の1日の労働時間はおよそ数時間だったと言われる。農耕が始まり、季節と収穫のサイクル管理が必要になると、日々の大半を費やす「労働」という概念が定着した。
産業革命以降は長時間労働が常態化し、現代では週40時間が標準。一方でリモートや時短など、多様な働き方が広がっている。要するに「働くこと」は生物一般の姿ではなく、歴史のある段階で強化された社会システムだという認識が出発点になる。
2. 会社が引き受けてきた“宗教的役割”の移行
近代以前、宗教は共同体の結節点だった。祈り・儀式・出会い・孤立の防止といった社会的機能を持っていた。世俗化が進むにつれ、その多くを会社が肩代わりしてきた。
- 共同体:同僚・部署・社内イベント
- 儀式:朝礼、表彰、年次行事
- 出会い:職場を通じた交友や配偶者との出会い
- 自己実現:仕事=自己表現・キャリア物語
この「会社の宗教化」は、AI・リモートワークの浸透で分解が始まる。賃金獲得としての労働と、自己実現・共同体参加は切り離され、別の場に移る可能性が高い。
3. AIがもたらす二つの未来
3-1. スーパー格差社会
AIを設計・運用し、アルゴリズムを支配できるごく少数が富と権力を独占。国家級の個人資産が現れ、その他大多数はAIと競合して価値提供が難しくなる。
キーワード:AIリテラシー、スケールする知能、資本×コードの複利
3-2. ベーシックインカムによる解放
一方で、巨大に蓄積された富の一部がベーシックインカム(BI)的に再分配され、働くかどうかは個人の選択になる社会も同時進行であり得る。
- ほとんどの人が最低限の文化的生活を享受
- 労働=義務から選好へ
- 忙しく働くことや資本の所有が、必ずしも尊敬や名誉の根拠ではなくなる
両者は対立ではなく表裏一体。上位は超人的に稼ぎ、同時に社会全体には最低保障が敷かれる――そんな二層構造が現実味を帯びる。
4. 「仕事=自己実現」は解体され再編集される
資本主義は、職業選択の自由を通じて「仕事=自己実現」という物語を育ててきた。しかし今後は、
- 報酬獲得としての仕事(短時間・高効率・AI補助前提)
- 自己表現としての制作・研究・ケア・コミュニティ活動(必ずしも貨幣化しない)
の二系統に分岐する。
将来の夢と職業は一対一に結び付かなくなり、「どんな生き方を編むか」の設計が中心になる。
5. 個人が今から準備できること
① AI補助前提の生産性設計
- 作業を分解し、自動化できる単位に刻む
- プロンプト力/ワークフロー設計/API連携で常時レバレッジ
- “自分×AI×ネットワーク”の三位一体でスケールさせる
② 再分配時代の“選好”を深掘り
- 何に歓びを感じるか(つくる/教える/育てる/治す/守る)
- 収入と意味を分けて設計する(ベーシック所得+創作・ケア)
③ コミュニティを再発明
- 会社以外の共同体(専門ギルド、ローカル、オンラインDAO)
- 儀式・学び・出会いを「場のデザイン」として意図的に組み込む
④ 名誉の新基準をアップデート
- 長時間労働や役職ではなく、他者への貢献、作品の質、継続性を指標に置く
⑤ “労働哲学”を言語化
- なぜ働くのか/働かないのか
- どれくらい働くのか(時間上限・下限)
- 何をもって“よい仕事”とみなすのか(価値基準・健康・家族との整合)
6. 10〜20年の見取り図
- 短期(〜5年):AI補助が全職種の標準に。リモート×成果主義が再加速
- 中期(5〜10年):一部領域で超人化が顕在化、所得分布の裾が厚くなる
- 長期(10〜20年):再分配制度が段階的に整備され、「働かない自由」と「猛烈に働く自由」が併存。労働観はパーソナライズされ、教育も“生活設計×創造性”へ
まとめ
AIは「労働の義務」を解体し、選べる生き方の幅を拡張する。スーパー格差とベーシックインカムという二つの潮流が交錯するなかで、必要になるのは各自の労働哲学だ。働く理由と働かない理由、働き方の時間配分、名誉の基準、関わるコミュニティ。これらを自分の言葉で定義し、アップデートし続けることが、AI時代のキャリア戦略になる。

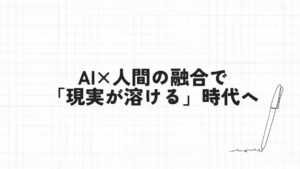
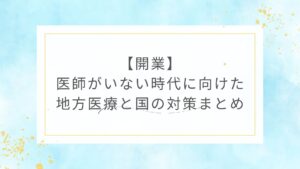
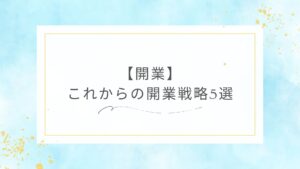
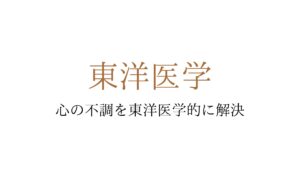

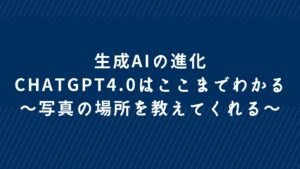
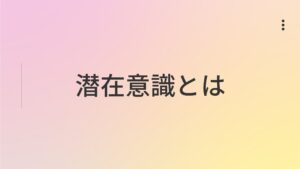
コメント